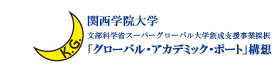2023.07.25.
【7月15日開催】上智大学・関西学院大学共催 スーパーグローバル大学創成支援事業シンポジウム
7月15日(土)、本学が包括協定を締結している上智大学との共催で、スーパーグローバル大学創成支援(SGU)事業シンポジウム「大学での学びは学生の成長に寄与しているのか~IRデータから見る学修成果と教育プログラムの質保証~」を開催しました。両大学はSGU事業を通じて、国際化だけでなく質保証を含む大学改革全般を推進しており、本シンポジウムは教学マネジメント、内部質保証の枠組みにおけるIR(Institutional Research)の活用に焦点を当てた各大学の事例紹介とともに、今後の質保証のあり方について議論を深めることを目的に企画しました。全国の大学関係者を中心に多くの関心を集め、当日は上智大学四谷キャンパスでの参加が45名(関係者含む)、オンラインウェビナーでの参加が225名となり、あわせて270名が参加しました。
.jpg)
プログラム前半では、文科省 高等教育局参事官(国際担当)の小林 洋介氏による開会ご挨拶の後、同志社大学社会学部山田 礼子教授が「日 本のIRの動向と方向性」をテーマに基調講演を行いました。IR研究の第一人者である山田教授からは、米国と日本のIRの発展過程の違い、学生 とIRの関係性等について発表があり、日米比較から得られた知見を基に日本のIRが抱える課題、そして今後日本でIRが定着し、より発展して いくために何が必要かということについての考察が示されました。
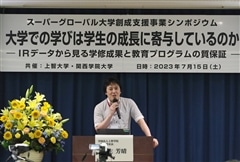
続いて、両大学より、教学マネジメント、内部質保証の枠組みにおけるIRの活用事例の紹介があり、上智大学の相生 芳晴IR推進室長からは①2022年度卒業時成長実感調査、②教育課程・学修成果10指標、③SGU指標学生語学スコアの伸長に関する分析結果について、本学からは、「Kwanseiコンピテンシー(KC)」に基づく学修成果の可視化の取組として、卒業後の人生まで射程を伸ばした効果検証についての報告がありました。


プログラム後半では、上智大学の伊呂原 隆学務担当副学長、相生 芳晴IR推進室長、鎌田 浩史IR室チームリーダー、本学からは村田 治前学長、小野総合企画部長・IR室長、藤田IR室員がパネリストとして参加し、基調講演及び両大学の事例紹介を踏まえ、 ①教員個人を教学マネジメントにどう巻き込むか、②直接評価と間接評価、③IR機能論、④学生の成長に資するIR・質保証という4つの論点で、今後の大学の質保証のあり方について、活発に議論を行いました。登壇したパネリストからは、「大学のIRを機能させるためには、データ分析結果を改善や実際の政策提言という形で実践に繋げ、それが学生の成長に還元されるようPDCAを回していくことが肝要」、「日本のIRは教学IRに加え、今後は経営IRにも拡張していくべきで、大学の政策立案とIRは不可分の関係になってきている」等の意見が交わされました。
議論の総括として、山田教授より、今後のIRのあり方として有意義な議論がなされたことに評価を頂きつつ、「日本の大学では教学IRを中心に成長してきたが、今後の潮流としては経営IRや研究IRも重視することになり、IRに多様性が出てくる。大学の規模によっては十分なIR推進体制が整備できないという課題もあるため、今後は大学間連携の検討が必要でないか」とのコメントを頂きました。
今回のシンポジウムでは、両校がSGU事業で推進してきた質保証の取組から得られた知見をもとに、今後のIRの在り方について全国の大学関係者の皆様と理解を深める機会を提供でき、参加者満足度も大変高い意義深いシンポジウムとなりました。
※写真提供:上智大学